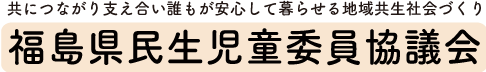≪民生委員・児童委員とは≫
- 民生委員は全国に約23万人おり、100年以上の歴史を誇る伝統ある制度です。
- 民生委員は、1917年に「済世顧問制度」が岡山県で発足し、翌年1918年に大阪府で「方面委員制度」へと名称を変更。1946年に「民生委員」と名称を変え今に至ります。
- 民生委員は民生委員法に基づく守秘義務があり、相談内容や個人情報などの秘密は厳守します。
- 民生委員は児童委員を兼務しており、年齢を問わず広く地域の「繋ぎ役」として活動しています。社協や行政、関係機関と普段から連携し、ケースに応じて「繋ぐ」ことが民生委員の主な役目です。
- 民生委員は、厚生労働大臣により任命され、市町村の決められた区域において、相談援助や見守りなど社会福祉に携わっています。任期は三年間(再任可)で、三年ごとの一斉改選により委員を推薦します。
- 民生委員・児童委員の一部(全国で2万人)は厚生労働大臣により「主任児童委員」に指名されています。「主任児童委員」は子どもや子育てに関する支援を専門に担当する民生委員・児童委員で平成6年1月に制度化されました。それぞれの市町村にあって担当区域を持たず、区域担当の民生委員・児童委員と連携しながら子育ての支援や児童健全育成活動などに取り組んでいます。
- 令和5年度からは「こども家庭庁」が設置されたことで、厚労省・こども家庭庁との連携により委員活動が進められます。
- 毎年5月12日は、済世顧問制度が公布された日にちなんで「民生委員・児童委員の日」として定めています。民生委員・児童委員の存在や活動について一層の理解を図るために各県で様々な取り組み、イベントを行っています。

民生委員・児童委員のマーク。四つ葉のクローバーと民生委員の「み」の文字と児童委員を示す双葉を組み合わせたもの。
民生委員児童委員信条
一.わたくしたちは隣人愛をもって社会福祉の増進に努めます
一.わたくしたちは常に地域社会の実情を把握することに努めます
一.わたくしたちは誠意をもってあらゆる生活上の相談に応じ自立の援助に努めます
一.わたくしたちはすべての人々と協力し明朗で健全な地域社会づくりに努めます
一.わたくしたちは常に公正を旨とし人格と識見の向上に努めます
≪民生委員児童委員協議会とは≫
- 民生委員法第20条に基づき、定める区域ごとに「民生委員児童委員協議会(民児協)」を設置しています。
- 各民児協は定期的に定例会を行っており、事例の検討やスケジュール確認など、その民児協独自の会議を開催しています。
- 市町村・区だけでなく都道府県・指定都市、全国にも民児協があります。
≪福島県民生児童委員協議会の取り組み≫
- 福島県民生児童委員協議会は事務局を福島県社会福祉協議会に置いています。
- 福島県の民生委員の定数は4853人で、各市町村で活動をしています。
- 福島県の民生委員は、東日本大震災による被害を受け、避難先で活動をしている委員もいます。市町村社会福祉協議会の避難者支援に携わる生活支援相談員と同行訪問をすることで、避難者の方が安心して生活できるよう努めています。
このような震災後の活動により、全国からも福島県の民生委員・児童委員の取り組みは注目されています。
令和元年に発行した福島県版「主任児童委員活動ハンドブック」への関心も高く、各県から参考資料として使用されています。さらに、昨今のヤングケアラーや虐待といった、複雑化した課題も顕在化されたことからハンドブックの改訂版を制作しました。
≪はあとふる・ふくしま≫
福島県社会福祉協議会で毎月発行している「はあとふるふくしま」に県内の民生委員の取り組みについてご紹介しています。詳しくは下記のリンクからご覧ください。
≪令和6年度福島県内民生委員・児童委員、主任児童委員を対象とした実態調査≫